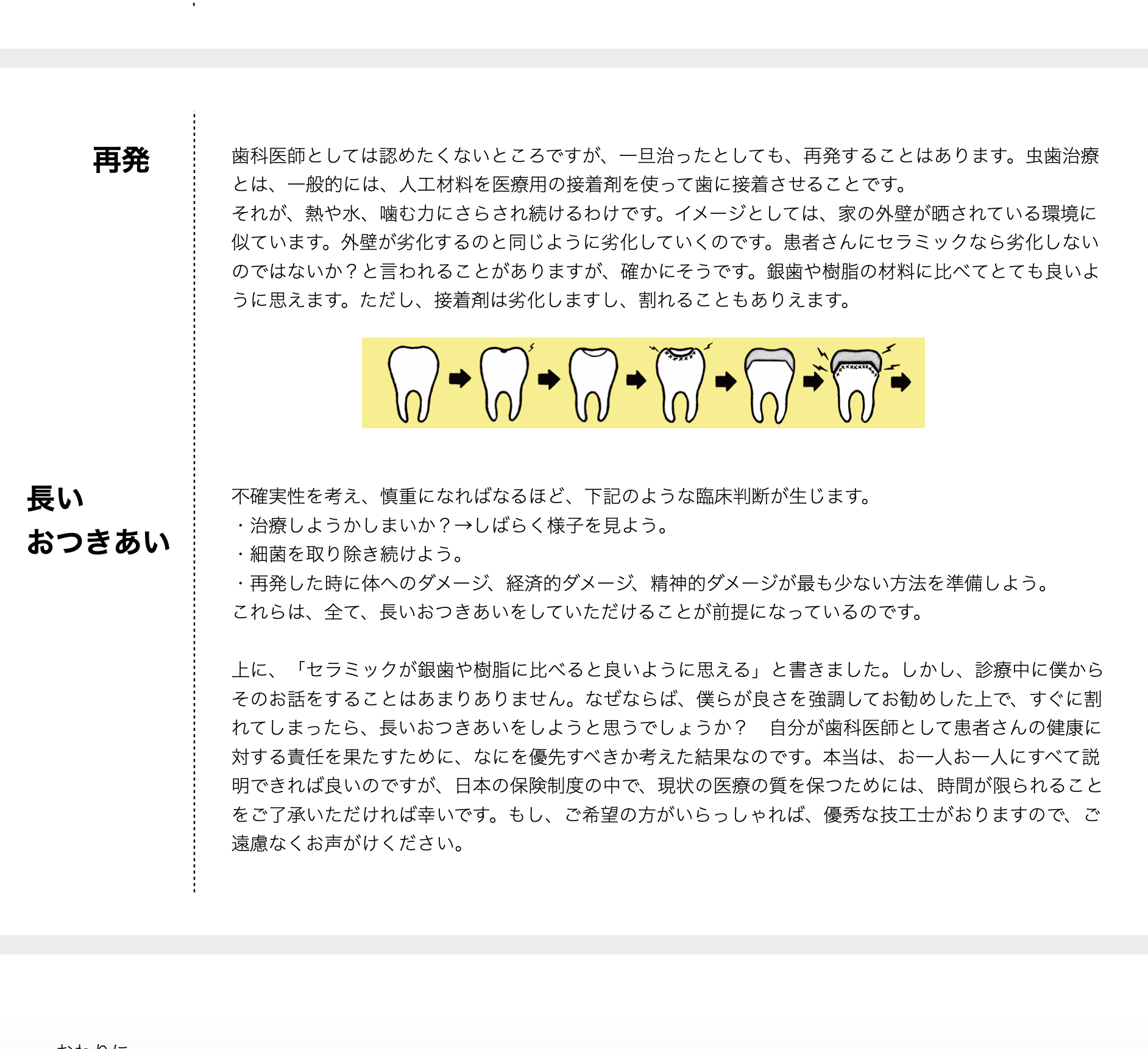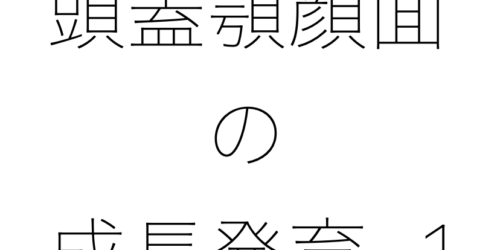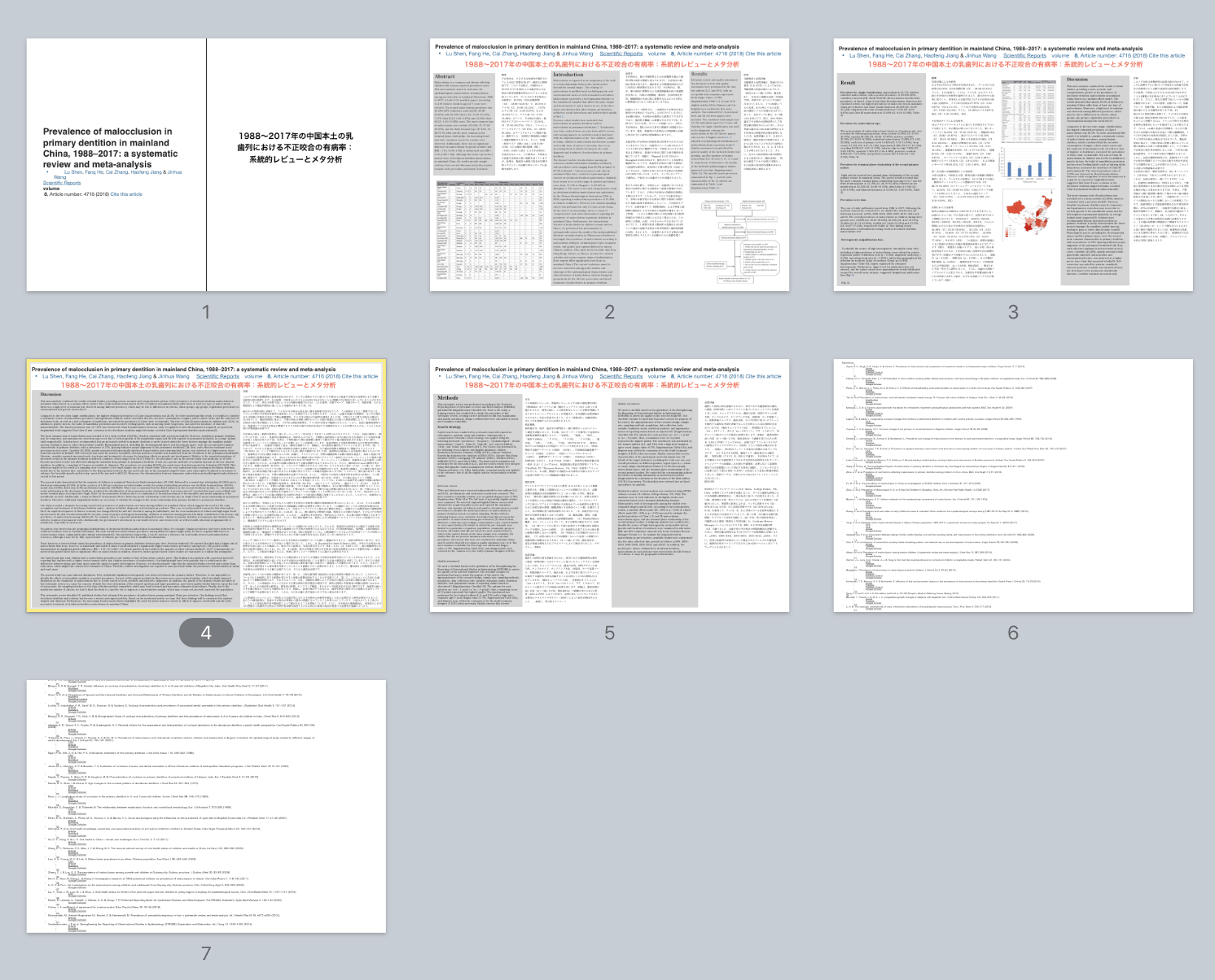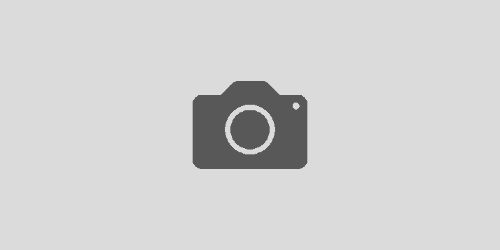-専門家向け-小児の嚥下の診断について
成熟型嚥下を獲得することが、顎顔面の成長発育において重要な鍵の一つである。(1)
成書を読んでも、事実の箇条書き的羅列が多く、診断の鍵が整理されていないように思える。
臨床家一人一人が思考を深めなければらない。
幼児型嚥下から成熟型嚥下への変化は、
「表情筋の動きがないこと」と表現される。
嚥下のチェックの際に、それがうまくできていたとして、
「日常的にできているのかどうか?」
という疑念が出てくる。
考えを深めてみたい。
「表情筋の動きがないこと」を本質的に考えれば、
ーー嚥下時における顔面筋肉の運動の分離ーー
と表現できる。
嚥下とは、舌と舌骨上下筋群の運動であるという前提で、それと顔面筋肉が協調しないということだ。
この前提で考えると、
「表情筋の動きがないこと」は
①無意識的に分離されている場合
と
②意識的に分離されている場合
に分けられる。
嚥下のチェックの際に、表情筋の動きのチェックをすることは、
単に表情筋が動くか動かないかではなく、 以下の4つを判別していることとなる。
A、動かない
A1 →①が獲得されている
A2 →②が獲得されているが、①は獲得されていない。
B、動く
B1 →①は獲得されていない
②はできるが意識できる時とできない時がある
B2 →①は獲得されていない②はできない
このようなグラデーションで判断すべきだ。
最低限、これぐらいは考えなければならない。
そうか。
「嚥下時に顔面筋肉の運動の分離」ができていればいいわけで、
極論すれば、嚥下時の表情筋の動きなんて関係ないとも言えるかもしれない。
わざと表情筋を動かすこともできるわけであるし。
ーーーー
嚥下のスタート時にどこが動くのかというのも重要な要素になるかもしれない。
①表情筋が動くことがシグナルとなり、反射的に舌が動く場合
②舌が動くことでシグナルとなって表情筋が動く場合
というのもあるかもしれない。
おそらくこの辺りの臨床研究は皆無だと思うので、
雑記になってしまったが、このような仮説を立てつつ取り組むと経験値の伸びが全く違うのではないかと思う。
文献