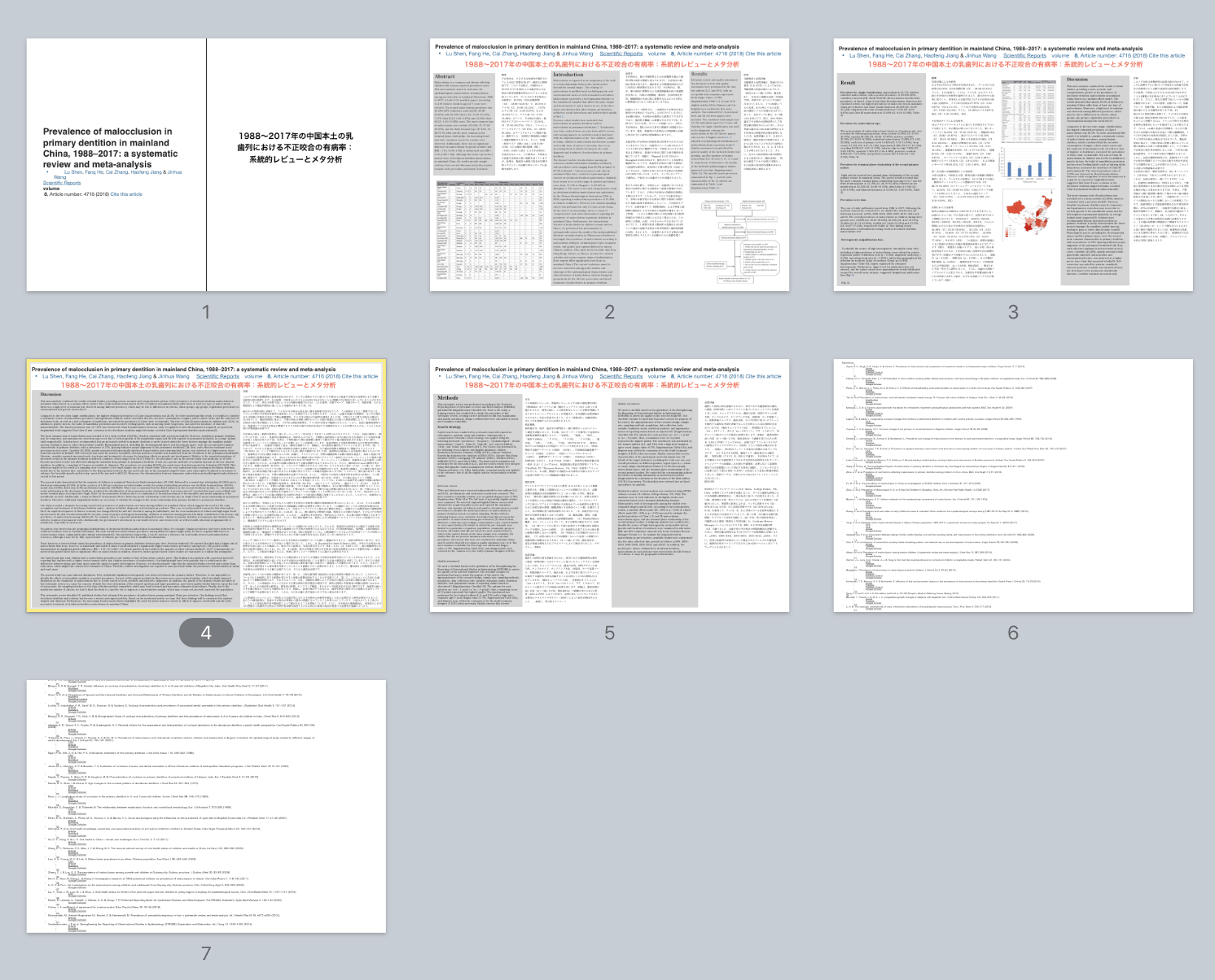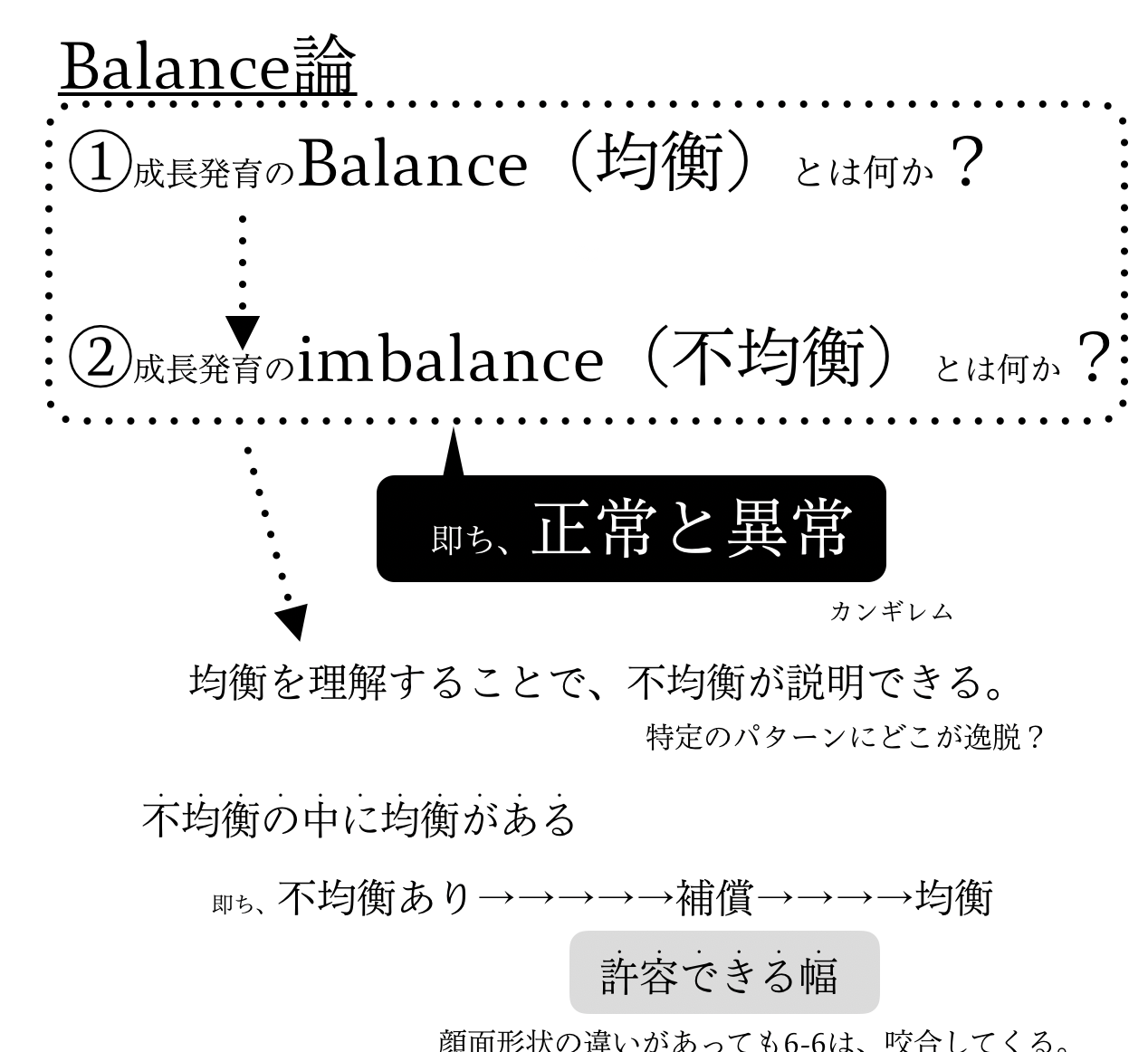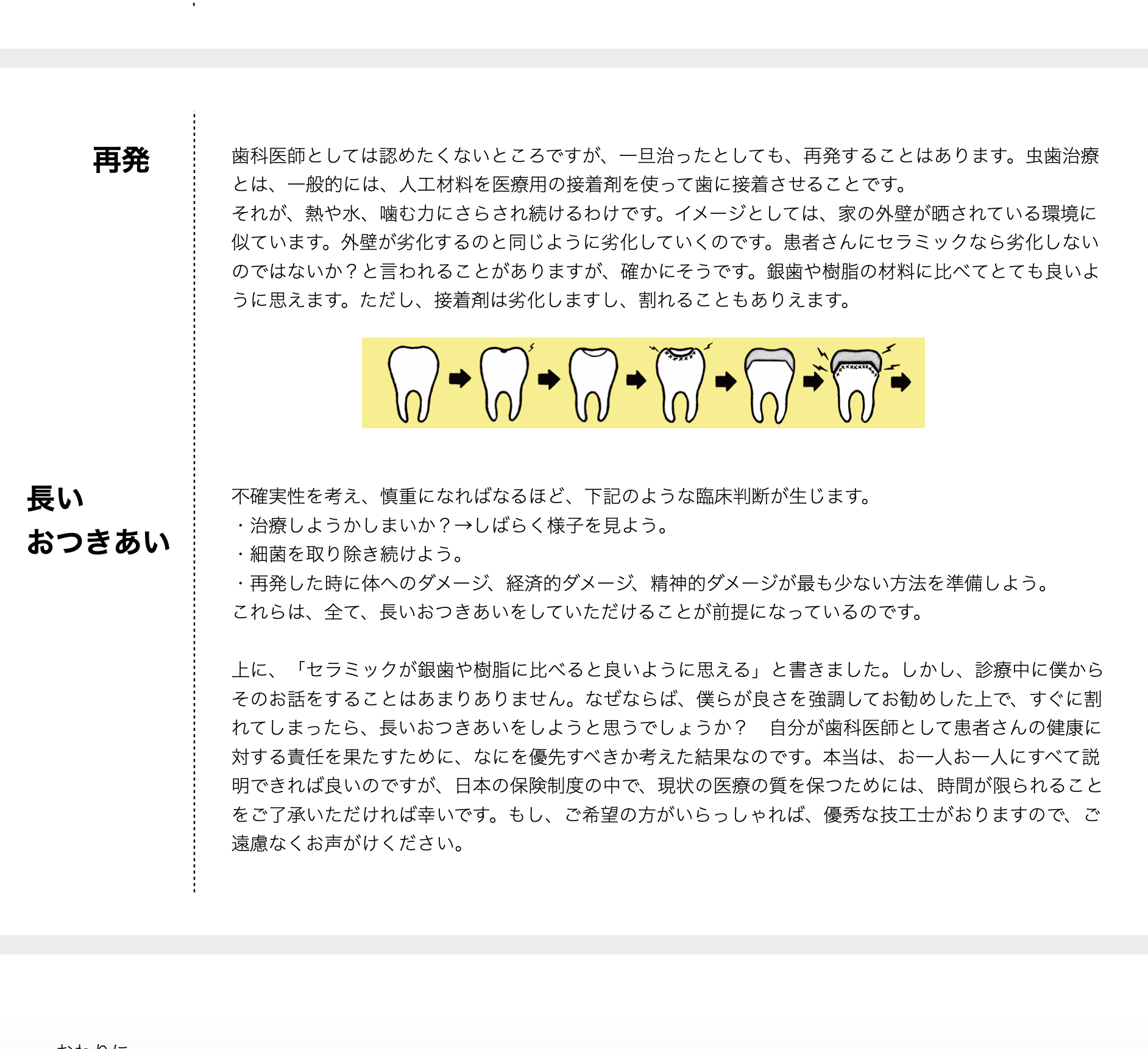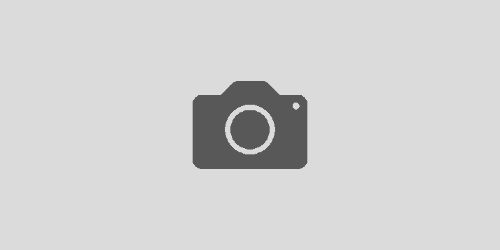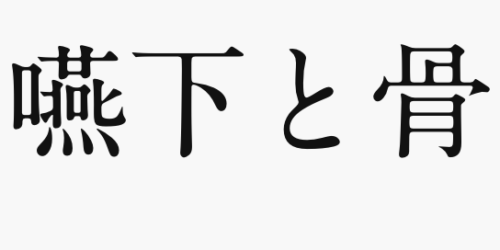不正咬合の有病率 その4
不正咬合というのは、「不正」と言われているだけで別に「病気」ではない。人それぞれの形態の一部であると言える。人それぞれの形態に、「不正」だのなんだのというのはどうかと思うところはある。
人それぞれの形態に、「その人の持って生まれたものでしょう。」と感じるのは極々自然なことであり、その背後には「遺伝だよね」という気持ちが隠れている。
歯科医学の中では、遺伝だけではなく、環境も形態を作ると考えられてきた。僕が大学で学んだときは、指しゃぶり、アデノイド様顔貌など、明確な特徴付けがされているものによって、環境要因が示されていたように思う。
つまり、「指しゃぶりがあるか。ないか。」「アデノイドが肥大しているかしていないか」という2分法的な捉えられ方をしていたように思う。
現実は、そのような2分ではなく、グラデーションに富んだものだと思う。そのようなものの存在を、科学的にデータ化するのは難しい。
では、どうすれば良いか。
僕は、子供の頭蓋顔面に対するアプローチを始めた頃から、不正咬合の増加率のデータをまず集めることが大事だと考えていた。
まず、このような二分法的な原因論では語れない環境要因の存在を数字で示すことができるのが、増加率だと考えたからである。
増加していれば「なーんかあるよね」という今までの対応の不足を示すことができるだろう
現在、口腔機能低下が不正咬合の原因となるという考えが広まってきており、対応が求められている。
不正咬合の増加率のデータを取っていくことが、その対応を後押しするのではないかと思うのである。