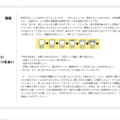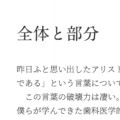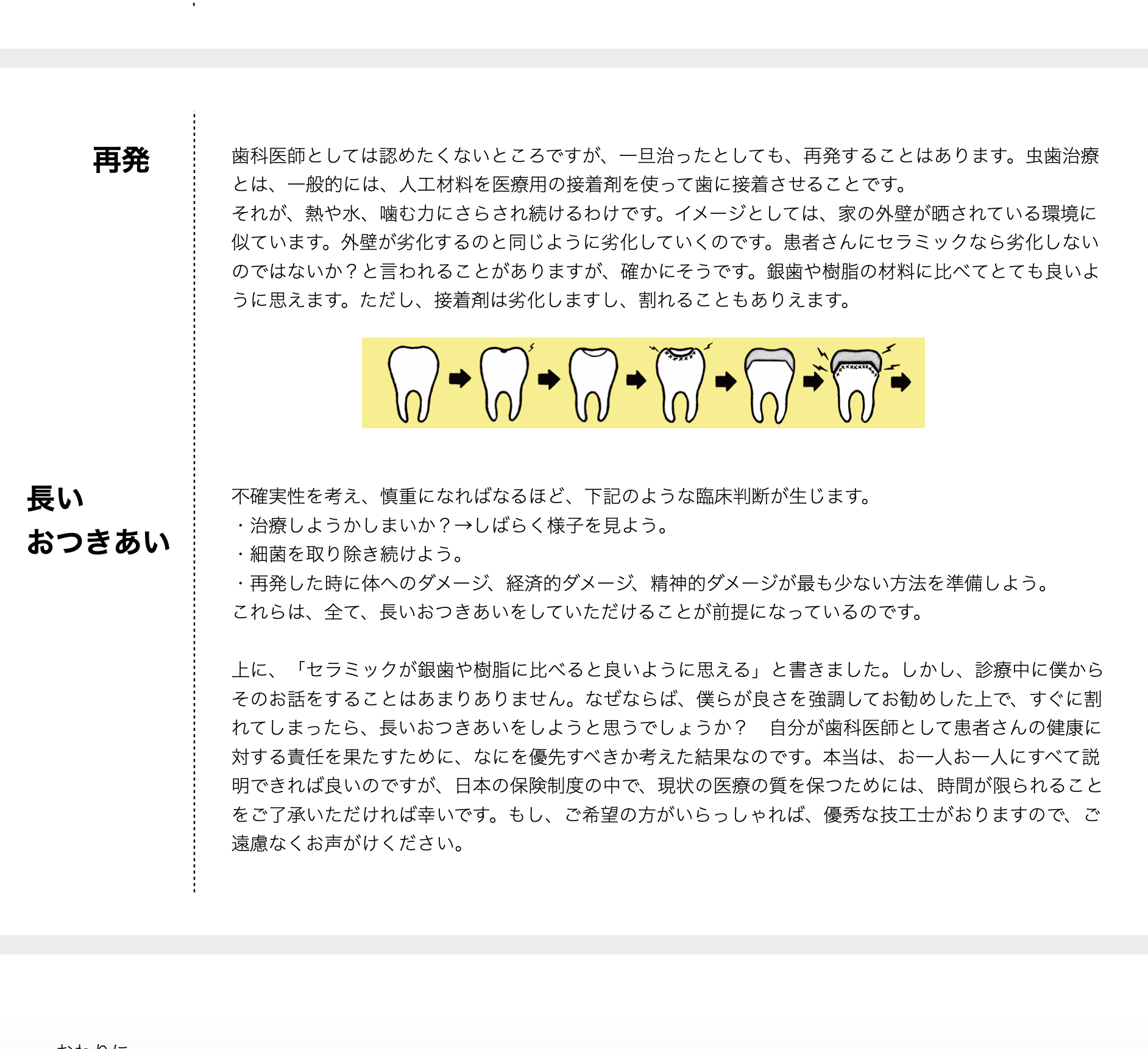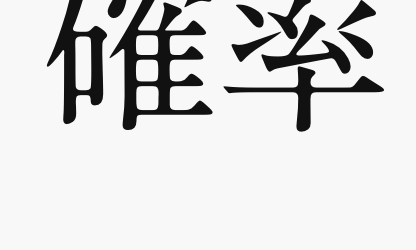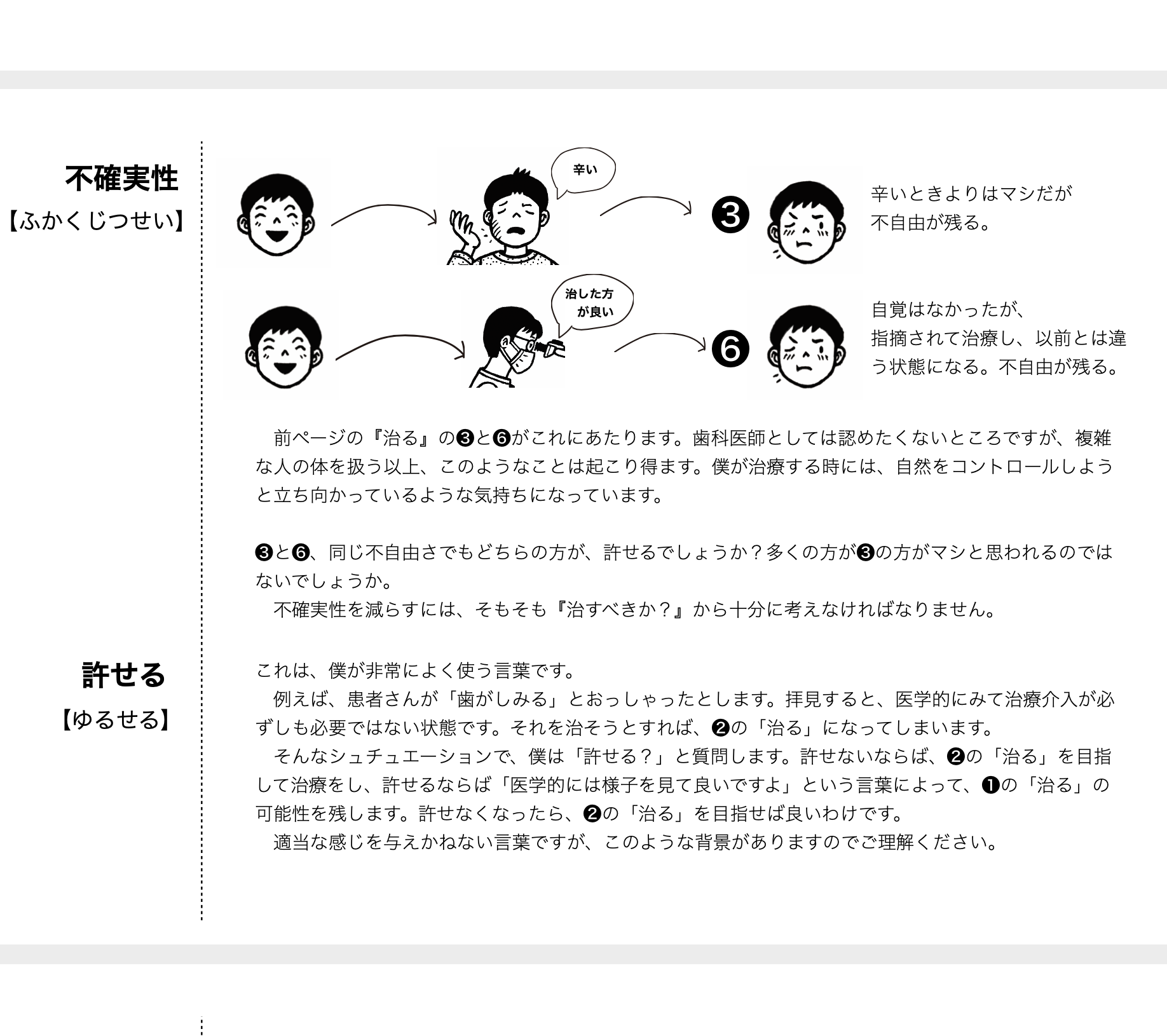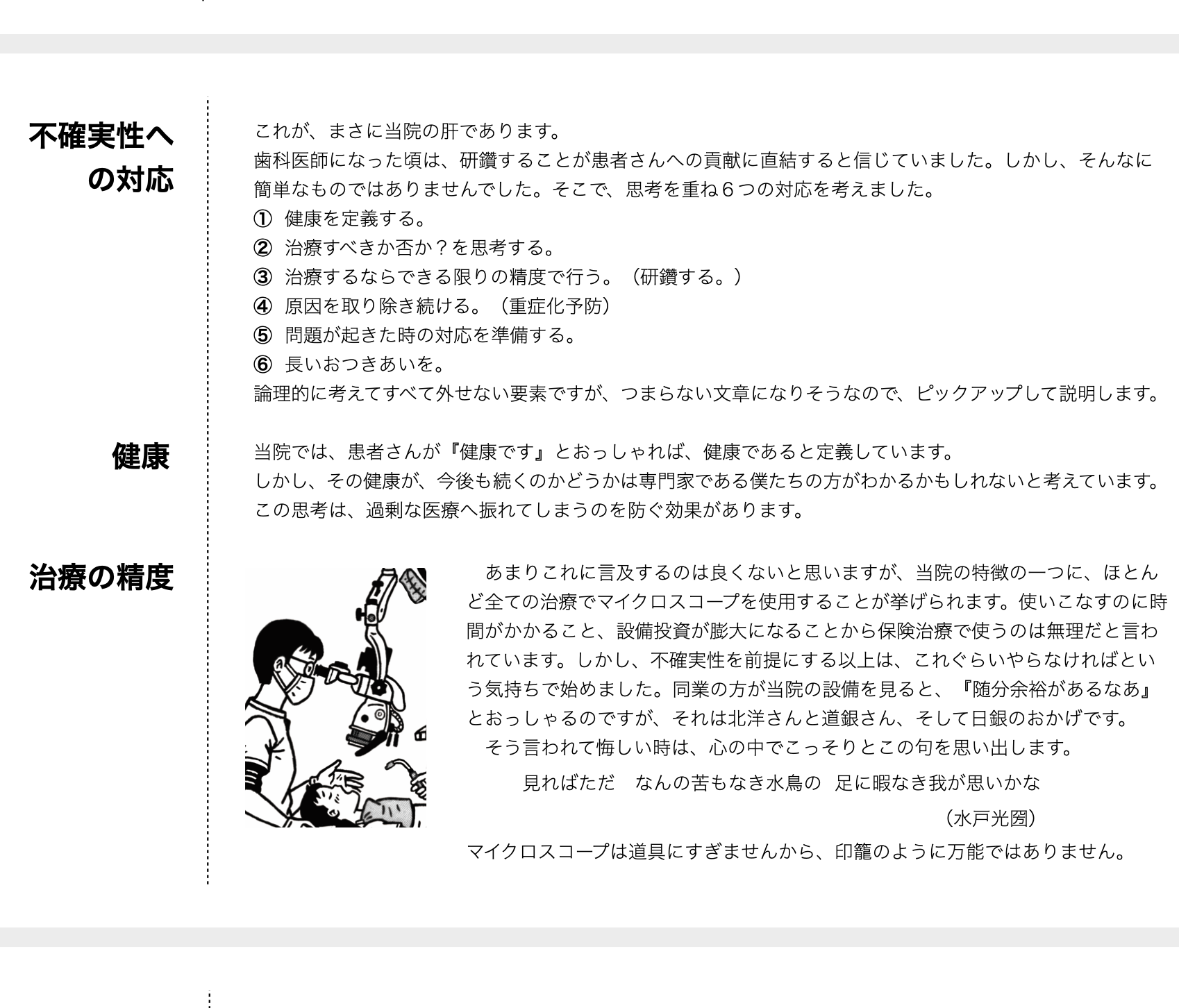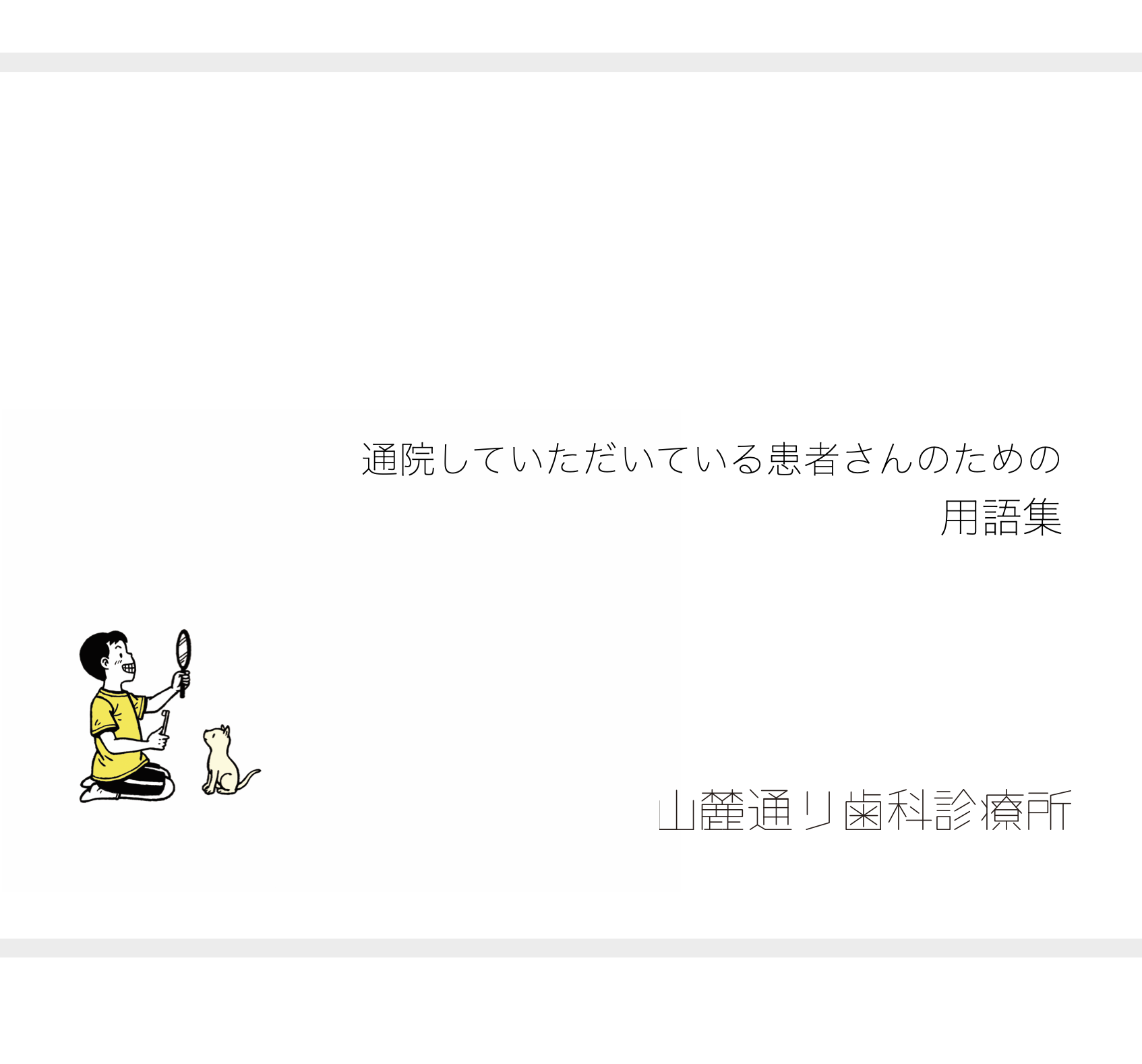歯を失ったとき
歯を失ったときどうするべきか?
患者さんにとっては大きな悩みとなっていることが非常に多いです。
webサイトの「考え」に書いたことの繰り返しにもなりますが、当院の考えを記載しておこうと思います。
ネットで検索してみると、インプラント、入れ歯、ブリッジのメリットデメリット。などが無数にヒットしてきます。
例えば、歯を失った方への「情報」として、インプラントと入れ歯のメリットデメリットを例にあげましょう。
インプラントのメリットは、他の歯に負担をかけずに済むこと、取り外しの手間がないことなどです。一方で、デメリットはオペが必要なこと、長期的なケアの問題などが挙げられます。
入れ歯の場合は、歯を大きく削らなくても良いことがメリットであり、一方で、取外しの手間、見た目の問題、違和感などがデメリットであります。
上記のような比較は、「情報」です。これを読むときに、気になるのは「正しいのか間違っているのか?」だと思います。
これらは「情報」としては正しいと思います。
ただ、ここから患者さん自身に適応するためには、「専門知」と「価値観」のフィルターを通さねばなりません。
情報と専門知と価値観に関してはこちらに説明したのでご覧ください。⇩
まずは「専門知」です。
上記の例で、インプラントも入れ歯もメリットとデメリットがあることがわかりました。ただ、これだけでは、自分に適応すべきかどうかわかりません。
ここで、「専門知」の出番です。このときに使う「専門知」はどういうことでしょう。
僕は、大きく分けて2つあると考えています。
① 個別性
② 複雑性
です。それぞれについて簡単に解説します。
① 個別性
まずは、患者さんの個別性を判断しなければなりません。それぞれの患者さんの残っている歯がどのような状態か、噛む力がどうなのか、などなどを踏まえて、メリットデメリットの重みづけをします。
② 複雑性
論理的に考えれば、個別性も複雑性に含まれる気もしますが、ここでは個別性を除いた複雑性とします。人の体のことで、我々がわかっていることなど1%もありません。つまり、解っていない99%以上の事柄を踏まえて考えなければらないのです。ここは、専門家でも様々な見解があると思いますが、「見えていないことをどのようにして見ていくか」というのは、臨床家としてとても重要な力なのではないかと考えています。
次に「価値観」です。
これは、「患者さんの」価値観であって歯科医師の価値観はどうでも良いということはとても大切です。
とは言え、患者さんが自分の「価値観」を明確に述べられることはほとんどありません。それを読み解くのが臨床家としての重要な能力だと思います。(僕もうまく出来ているかわかりません。。。)
僕の場合、患者さんと対話するときは、「専門知」を織り交ぜながら「情報」を提供していきます。その時の患者さんの反応、具体的には言葉はもちろん視線や表情の変化を見ながら価値観を推し量ります。患者さんの「顔色をうかがいながら」という感じかもしれません。顔色によって、選択肢に重み付けをしながら話を続けます。
患者さんがどうしても迷ってしまう場合は、「そんなに急いで決めなくては良いのでは?」と思うことが多いです。歯を失うということは、今後も他の歯を失うリスクが高いわけですから、定期的な管理が必要となります。
その時間を積み重ねることで、僕らは患者さんの価値観を推し量れますし、患者さんは僕らが信頼に値するかを判断できます。
あとは、「とりあえず後戻りできる方法から選ぶ」というのも重要です。その点、まずは医療保険適応の入れ歯で様子を見るというのは合理的です。
体へのダメージ的にも、経済的にも後戻りしやすいですし、それをケアしながら時間を重ねて判断すれば良いのです。
実際、とりあえず、この方法を選ぶことが一番多いように思えます。
いずれにしても、複雑なことですから、ネットで調べて答えが出るような事では無いのは間違い無いと思います。
なんとなく伝わったでしょうか。